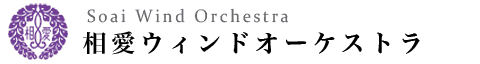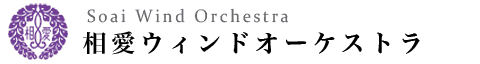2.表面の調整をする
準備するものはホームセンターなどで売られているサンドペーパー、そのなかで私はA4ほどの大きさで売られている少し厚手の耐水ペーパー400番を使っています。数字が小さいほど目が粗くなります。使いやすい大きさにカットします。
右の写真を見て下さい。リードの表面をあまり力を入れすぎないで、表面のざらつきを取り去ります。 ここでは削るというより、製造時に残された表面の削りカスを取り去る、といったことが目的です。
この時点で、もう一度吹いてみます。くれぐれも水分を与えないように注意して下さい。ちょっと重いかな、まだまだ硬いな、と思うくらいで止めておきます。
このあとはもうちょっとさわりたいと思ってもガマン。どのくらい硬いかを覚えておきあすに持ち越します。 |
 |
※微妙ですがサンドペーパーの丸めかたやリードに加える圧力にコツあり。
(画像クリックで拡大) |
|